
Original Update by Kentaro IEMOTO
ちょっと気になるニュースが…。
先日韓国で大韓航空の女性副社長が自社の旅客機に乗った際、機内サービスのピーナッツが袋ごと配られたことに腹を立て、乗務員をこっぴどく叱りつけ責任者を降ろそうと、離陸しかけた飛行機を戻したことが大問題になっているようです。
題して「ピーナッツリターン事件」というらしい。
このネーミングには思わず笑ってしまいましたが、大騒ぎになっているのに笑うのは不謹慎なのでこらえます。
私が興味を持ったのは、この女性副社長が財閥の娘で傲慢だからとか、ワガママだからとかあるいは韓国における財閥の横暴さとか、そういうところではありません。
彼女が、ピーナッツを袋ごと配るのは会社のマニュアルに違反していることに腹を立てた。すなわち「なぜマニュアルを守らないのだ!」という彼女のマニュアル至上主義に興味を持ったのです。
マニュアル至上主義の危険性
この事件、彼女の横暴ぶりやワガママという個人的資質に報道の焦点が当たっていますがあえて彼女の立場に立つなら別の側面も見えてきます。
大韓航空のマニュアルによれば、乗客へのサービスとしてピーナッツはちゃんと皿か容器に入れて出さなければならない。
にもかかわらずスタッフは袋ごとポンと出した。
これは明らかな服務規程違反であり、乗客に対するサービス精神の欠如であるといえます。
大韓航空の副社長すなわち経営者の一人として、これは見過ごすことの出来ない事態と考えスタッフや責任者を厳しく叱責したのなら、これはこれで彼女の行為に正当性があると言えるでしょう。
マァ、彼女の問題は「たかがピーナッツ」というささいなことで「多くの乗客にもっと大きな迷惑をかけた」という点でしょうか。
空港というところはご存じのように分刻み秒単位で飛行機の離着陸が行われており、管制官は空の交通整理に神経をすり減らしています。
バスじゃあるまいし離陸体制に入った飛行機がノロノロ引き返してくるなど大事故につながりかねません。
もし報道されているように、彼女が自らの権力を誇示するためにそんなことを命じたのなら言語道断であり、弁解の余地はありません。
厳罰に処されて当然です。
それでも彼女のマニュアル至上主義が、そのようにバランスを欠くほど強かったのだとしたら、それは現代的な問題として私の関心をひいたということです。
マニュアル社会の到来
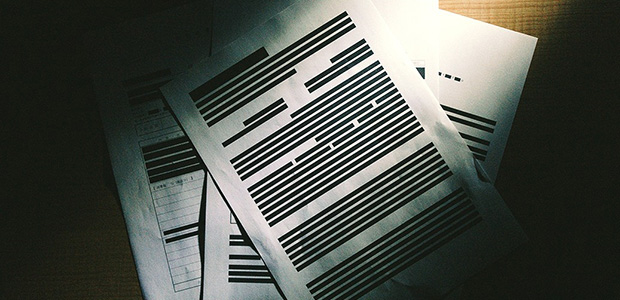
韓国の事件ほど極端ではないとしても、私たちの周囲でも似たようなことはあるのではいでしょうか。
会社でも役所でも病院、学校どこでもマニュアルなくして仕事は成り立たないといって良いくらいです。
窓口や電話での応対にも一定のマニュアルが必要ですし、学校の先生も授業をやる際には指導書というマニュアルを使うのがふつうです。
地震や火災などの緊急時には、特に病院や学校など多くの人命を預かる施設など、誰がどの患者(生徒)を率いて逃げるのか脱出経路はどうするのか、あらかじめマニュアルで決定しておかなかったら大変なことになります。
これなど絶対必要かつ守るべきマニュアルです。
現代のように社会が高度に複雑化し、求められるサービスの質も多岐に渡る以上、様々な事態を想定したマニュアルが存在するのは当たり前なのでしょう。
むしろそのようなマニュアルを作らない組織こそ怠慢なのです。
まさにマニュアル社会の到来です。
…とここまでマニュアルの必要性を認めた上で、あえてマニュアルの問題点も考えてみたいと思います。
実例で見るマニュアル至上主義の弊害
まずマニュアルとは何か。
マニュアルとは仕事の手順を記した「手引書」のことであり、業務にあたり当然知っておくべき最低限の知識を指します。
この「最低限の…」というところを押さえなければなりません。
いくら「マニュアル通りにやった!」と言っても最低限の仕事をしたに過ぎないということです。
それどころかマニュアルに縛られ型どおりこなしても、仕事の質そのものを高めることにはなりません。
ましてマニュアル至上主義におちいると、先の大韓航空の女性副社長のように本末転倒の結果を引き起こすことになりかねません。
一時「マニュアル人間」という言葉がはやりました。マニュアルに書いてあることしかできない若者を揶揄することばですが、これなどはマニュアルに縛られるあまり想定外のできごとに対応できない人間が増えていることを指しているのでしょう。
つまりこういうことです。
何でもマニュアルがありそれに頼っていると、創意工夫や臨機応変の才を欠き、自分の頭で考える努力をしなくなる。
マニュアルが最低限の知識である以上、本当は想像力を使ってそれ以上の“結果”を生み出す努力をしなければ真に良い仕事をしたとはいえないはずです。
たとえば塾や予備校などでも良く生徒に「傾向と対策問題」をやらせます。
これは試験に出そうな問題をまさに想定して「これが出たらこう答える」というマニュアルを生徒に覚えさせているわけです。
しかし少し視点を変えた問題 ―解が1つとは限らない問題や自分の考えを自由に述べよ― などが出ると、途端に頭がまっ白になる生徒が続出します。
特に難問というほどでなく、その場で落ち着いて考えれば十分できる問題でも想定外(マニュアルに書いてない)というだけで回答できないのです。
これも形は少々違えど、マニュアル至上主義の弊害といえるでしょう。
また企業の「お客様相談センター」なども、顧客の苦情対応マニュアルに頼り過ぎることがあります。
「お客様の苦情には逆らわず話をひたすら聞け」と言われているのか、そのバカ丁寧な口調と話を聞き流されている感がかえって客のイラだちと会社側への不信を募らせることも珍しくありません。
これなどはマニュアルの目的が会社など組織の防衛のため、自分たちを守るためのものになっているからです。
マニュアルは社会の円滑な運営に欠かせないものですが、一方において過度なマニュアル依存が人と人との暖かい交流や高度なサービスの創造をかえって阻害する傾向にあることを自覚したいものです。
マニュアルを基礎知識として十分に尊重しながらもそれを越えた創造的な仕事を常に心がける。
こういう姿勢こそが大切なのです。






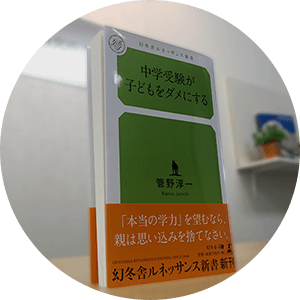
コメントはお気軽にどうぞ