
私は高校教師、塾講師を30年以上勤めて来てその経験から1つ確信していることがあります。
それは生徒の成績を上げる、入試に合格させることは簡単とは言わないまでも、そんなに難しいことではないということです。
たった1つの原則を守れば良いからです。
その原則とは「生徒を信じること」です。
教える側、つまり教師が生徒の能力(才能)をまず信じているということが教育活動の絶対的な前提であり、その前提があって始めて諸々の創意工夫―授業法や教材作成、動機づけや個別学習法やら―が活きてくるのです。
私が生徒の能力を信じるというとき、その根拠は2つあります。
1つは心理学や脳科学ですでに常識となっている「人間の脳は潜在能力の5~10%しか使われていない」という事実。
もう1つは、私のこれまでの経験から導き出された人間観察の結果で、多くの人は自分の能力を「実際より低く見積る」傾向があるということです。
要するに、人はただでさえ自分の能力のほんのわずかしか使っていないにもかかわらず「自分には才能がない。どうせダメだ」と始めからあきらめる傾向が強いということです。
最初の「脳は全体の5~10%しか使っていない」という話は、もし全ての力(100%)を出し切ってしまったら生命にかかわるからという説があり、そのため普段は緊急事態に備えてこの程度に押えていると言われています。(だから緊急時には火事場の馬鹿力となるわけです。)
つまり強い危機感―生命にかかわるような―を抱いたとき、人は脳の「ヤル気スイッチ」をオンにするわけです。
入試が近い。次のテストで良い点を取らないと大変なことになる。
このような状況で生徒がすさまじい集中力を発揮してそれまで考えられなかった伸び方を見せるのは良くあることで、まさにスイッチが入った、脳の潜在力が一気に開花した瞬間といえます。
ただしこれは生徒自身が危機感を感じて、自発的にヤル気スイッチを点火した結果だから良いのであって、もし教師の側が「危機感」をあおり生徒を常に追いつめるやり方で「ヤル気スイッチ」を押し続けるなら、一時的に効果は上がっても永続的な効果は望めないでしょう。
この方法は、賞罰を与えたりスパルタ方式で生徒の欲や恐怖感に訴える、いわゆる外発的動機づけといわれるもので既に一時的効果しか生まないことは証明されているのです。
なので大切なことは、生徒自らが「自発的にヤル気スイッチを押す」よう促すことにあります。教師の仕事はこれに尽きるといってよいでしょう。
そのときもっとも有効な方法こそが、私の経験では「人は自分の能力を実際より低く見積もる性質」を解除すること。その思いこみを解いて「自分にもできるかも知れない」と思わせることであり、その前提として生徒の能力を信じることが必要になるわけです。
教師のおちいるワナ
ところが残念なことに、教える側の先生自体が生徒の能力をそれほど信じていないことも多く、信じていないからこそ生徒が能力を発揮し切れていないのだということも認識していない。つまり悪循環におちいっていることがよくあります。
教師は生徒をどこまで信じ切れるのか
この問題は実はかなり根深い、一筋縄では解決できない原因があると思っています。
それは1つには教師の心理的問題にかかわるからです。
たとえば学校などでも、熱心という評判の先生はたくさんいます。しかし熱心イコール生徒を伸ばす先生とは限らないのです。
ここに「熱心な2人の先生」がいるとします。
1人は、生徒の能力をシンプルに信じ熱心に指導する先生。もう1人は「生徒は世話の焼ける存在」であり「出来ない子ほど細かく見てあげないとダメだ」と信じて熱心に指導する先生。
どちらが生徒を伸ばす先生でしょうか。
少し考えて下さい。
私の経験では前者の「生徒の能力を信じている」先生のほうが生徒を伸ばすといえます。
後者は生徒本人や親から感謝されることはあっても必ずしも学力向上という点では、大きなパフォーマンスを上げるとは限らない。
なぜなら後者のタイプの先生は、基本的に生徒の能力を信じていないからその「不信感」が生徒の心理に微妙に反映されているからです。
さらにここにはもう1つ、恐ろしい問題が横たわっています。
それは― このタイプの先生が教師という職業を選んだそもそもの動機自体に秘んでいる問題です。
何でしょうか。
ここから先は微妙な問題を含むので書き方が難しいですがガンバって書いてみます。
教師を仕事に選ぶ人は、一般的に子供好きで優しく思いやりのある人が多いのは確かで、子供たちのために尽くそうという使命感をもっているものです。
そしてそのことが裏目に出ることもあるのです。
どういうことか?
「自分こそが子どもたちを導びいていくのだ」という使命感は、「導びかれる子どもたち」がいて始めて本領発揮されるわけです。すなわち教師の使命感が満たされるためには「ダメな子どもたち」の存在が欠かせないということです。
子どもたちがダメであればあるほどつまり自分たちが苦労すればするほど彼らの教師としての達成感は満足するわけです。
この逆の現象がいわゆるピグマリオン効果です。
ピグマリオン効果というのは、教師がたとえば自分のクラスの生徒は皆優秀だと信じ切っていると、生徒たちの学力は伸びるが逆だと伸びない現象のことで、教育界では実験でも確認された有名な法則のことです。
しかし私の経験では、多くの教師(塾講師も含めて)がこの「法則」を知ってか知らずか生徒の潜在能力をあまり信じていないのです。特にあまり成績が良くない子たちに対して「彼らは出来ないから面倒をみなくては・・・」と使命感をますます強めて接するのです。
「彼らは出来ないから」という教師側の思いこそがまさに「出来ない子」を出来ないままに固定しているのだということに気づかないのです。
そうしてますます「出来なくなる生徒たち」を前に教師は「だから自分がいてやらないとダメなのだ」と、授業のレベルを下げたり進度を遅くしたり、宿題を減らして一層生徒の力を低位置に固定していきます。
これが先に述べた悪循環であり教師のおちいりがちなワナなのです。
いずれにせよそこには依存ともたれ合いの不健全な関係が生じています。
生徒を信じると学力は上がる
生徒を伸ばし学力を上げることは、生徒の潜在能力を心から信じるだけでかなりのレベルまで達成されるというのがピグマリオン効果からも、私の経験からも確信していることです。
何も特別の秘策とかメソッドとかが必要なわけではなく、ただ生徒の能力をひたすら強烈に確信するという教える側のあり方が何よりも重要だということです。
「ただ信じるだけ?」
「そんな簡単なことで伸びるなら苦労しないよ!」
そんな声が聞こえて来そうです。
1つ誤解のないように言いますが、生徒の能力を信じるというのは生徒を甘やかすとか、現状のまま放置するということではありません。それどころか、私の場合でいうと相当厳しく生徒を指導することになります。
宿題をやって来ない。約束したプランを実行していない者にはメチャメチャ叱りつけ、場合によっては立たせたり家に追い返すことさえします。なぜでしょうか。
生徒の能力を信じているからです。
多くの生徒―生徒に限らないが―は自分が考えているよりはるかに高い能力をもっているのです。(その根拠については先に述べました)
伸びないのは―例外はあるが―単にサボっているだけであり、自分の能力を出し切る経験がないからムリだと思いこんでいるに過ぎません。
生徒の現状(低レベル)にこちらが合わせるのではなく、こちらが判断するその生徒の最大値まで生徒を引き上げるのが指導者のあるべき姿だと思うからです。
だから当然指導は厳しくするのが原則ですが前提に「生徒に対する愛情と信頼」があれば必ず伝わり、それはこちらへの「信頼」となって返ってきます。
その信頼関係が生徒の「学力」や「行動」に対する「やる気スイッチ」につながることになります。そこには妙な依存やもたれ合いの入るスキマはありません。
とても言いにくいことですが、生徒を伸ばし切れない先生の中には「手取り足取り熱心に教える」ことによって自己満足に浸っている人も多いのです。その自己満足と引き換えに本来もっと伸びるはずの生徒が可能性を閉ざされているのも事実です。
それは結局のところ、生徒を信じていないか自分が生徒に依存されることを望んでいるかそのどちらかであるのです。
熱心な先生という響きは心地よいものですが、その言葉に酔って教師本来の役割を忘れてないか。私も含め、人を教える立場の者は常に我が身を振り返る必要があると思っています。
教師は生徒の表面―外に現われている姿―だけを見るのではなく隠れた能力を見抜き、その潜在能力が発揮された姿をイメージしてそのレベルまで引き上げることにこそ情熱を注ぐべきではないでしょうか。
生徒指導に悩んでいる先生方と話す多くは真剣に生徒のことを考えているのが伝わって来ます。しかし私が上のようなことを言うとたいていの先生方は「ハッと」するのが分かります。
現状の問題点ばかりにフォーカスしすぎて「生徒を信じる」という基本を忘れていたのではないか・・・という思いです。
良心的な先生方の中にも「ダメな生徒を一生けんめい指導してやっている自分」という、高見から生徒を見下ろす部分が秘んでいることもあります。その思いこそがダメな生徒をつくり出しているのかも知れないと自覚すればそのとき真に良い教師になることができます。
今日の話。教師のあり方が中心でしたが親子のあり方や会社での人間関係にも基本的には同じことが言えるのではないかと思います。






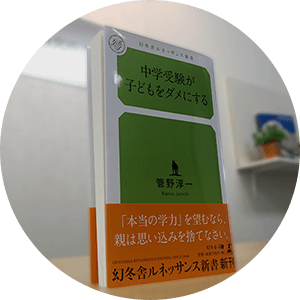
コメントはお気軽にどうぞ