学校と近代について【管野・庄本スペシャル対談】

管野
まず庄本先生の「勉強観」について話してください。
庄本
昔から、なんでみんな勉強というものを嫌がるのかな、というのが自分の中ですごく大きな疑問としてあったんですよね。で、自分自身は「勉強」という行為をあまり特別なものと考えていなくて、自分がなにかを手に入れたら、それは全部勉強だって思っていたので。
管野
手に入れたものが全部勉強、うん。
庄本
例えば、お皿の洗い方を覚えたのも1つの勉強だと思っていましたし。でも、ひょっとしたら自分の中にある勉強観が世間一般のものと違うのかもしれないと思い始めて、それを管野先生や塾の先生たちと話をしていく中で、やっぱり世間一般の勉強の考え方というものをもう一度整理して問い直してみると面白いのではないかな、と。
管野
まあ、私は子供時代から「覚えろ」とかテストの点数で縛るというのは反発があるわけ。で、小学校に入った時にものすごい悲しい、というか違和感があって、校舎に入って上履きに履き替えてネームプレートをつけて、体育館で「前へならえ」させられて、ちょっとでも動くと「そこ、何だ!」と叱られる。校長先生が壇上に上がるまでにものすごく“儀式”があるわけですよ。決められたとおりに全体が動かなきゃならない。ある意味、自由を奪われた。大げさに言えばね。囚われの身になった。僕に言わせれば小学校に入学するって体験自体がトラウマ。
庄本
ああ…(笑)。
管野
日常生活の世界から一歩校門くぐると、校庭からすでに別世界なんですよ。あの違和感ていうのがずっと抜けなかった。だから25,6になって高校の非常勤講師をやった時も、学校に入って行くとシーンとしてて、なんかこう、ストレス…。だから教師を続けなかったんですけど(笑)。あのストレスフルな雰囲気は、「窮屈さ」を感じさせる。
庄本
その独特の雰囲気は、学校が本来学問をやるべき場所なのに、学問と規律の部分が逆転しちゃってるというか、学問自体が規律に奉仕するような状態にシフトしてしまっているがゆえなのかもしれません。それがなぜなのか、明治時代から学校の歴史を色々調べてみると、やっぱりそこに大きな背景がありました。
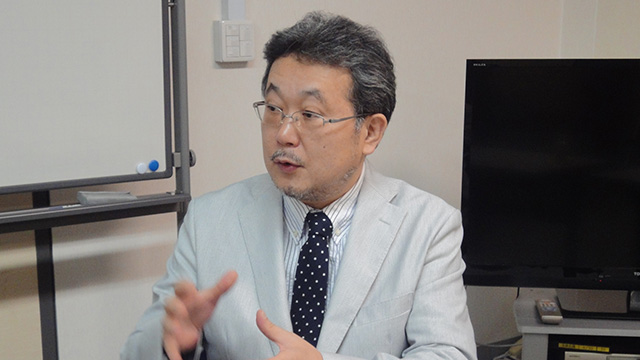 管野:うん。それって学校の持つ性質なのかな、初等教育のね。ヨーロッパでもそうでしょ。19世紀になって産業革命以降のヨーロッパにおいては、子供はある種、働く人材であり、働くためには読み書きそろばんができないといけない。それから上から言われたことをちゃんときかなきゃいけないとか。なんか性悪説があるような気がするんですよ。自由な人間は社会にとってはやっぱり好ましくない。自由な発想、行動。だからやっぱり鋳型にはめなきゃいけないわけだ。
管野:うん。それって学校の持つ性質なのかな、初等教育のね。ヨーロッパでもそうでしょ。19世紀になって産業革命以降のヨーロッパにおいては、子供はある種、働く人材であり、働くためには読み書きそろばんができないといけない。それから上から言われたことをちゃんときかなきゃいけないとか。なんか性悪説があるような気がするんですよ。自由な人間は社会にとってはやっぱり好ましくない。自由な発想、行動。だからやっぱり鋳型にはめなきゃいけないわけだ。庄本
それこそまさに近代の特徴ですね。近代国家というのは一般大衆というものが必要だと思うんですね。兵士の予備軍である・労働力の予備軍である。彼らは規格大量生産の担い手だから、他の人と違う発想をしたり違う行動をされると困るわけです。そういう労働力の確保というのはそれまでの農村社会、伝統的な商工業のシステムではダメで、都市部の一般大衆を必要とする。日本もまさにその近代国家を創るために、そういう人材を教育するために、鋳型にはめるために学校というものを作った。
管野
一方で、国家の部品にならない、国家をコントロールするエリートも必要になる。でも、エリートと大衆は区別して、大衆は教育してやる、と。その教育の中には規律とか非常に大きな部分を占めていて、最低限の勉強だけできればいいという。それが日本にも来ているのかな。ヨーロッパの場合学問の伝統は大学にあると思うんですよ。そこでは一部のエリートが「学問は自由だから」と自立した学問を追究した。そして、代々続く自由のエッセンスは、少なからず一般大衆への教育にも影響を与えている。
 庄本:ヨーロッパから日本に輸入された教育という部分だと、近代の学校制度の基はナポレオンがかなり作っているんですね。特に有名なのがフランスのエコール・ポリテクニークというは理系の学校です。ここでは官僚や技術者を国家の力で一気に作りあげていく。面白いのは、このようにナポレオンが作った教育機関と並列して、中世から代々続く昔ながらの大学も力を持ち、上手く融合していくところなんです。管野先生がおっしゃっていた「自由な学問」は特にこの昔ながらの大学に保存されています。これは実は、明治期以前の日本と似ていますよね。
庄本:ヨーロッパから日本に輸入された教育という部分だと、近代の学校制度の基はナポレオンがかなり作っているんですね。特に有名なのがフランスのエコール・ポリテクニークというは理系の学校です。ここでは官僚や技術者を国家の力で一気に作りあげていく。面白いのは、このようにナポレオンが作った教育機関と並列して、中世から代々続く昔ながらの大学も力を持ち、上手く融合していくところなんです。管野先生がおっしゃっていた「自由な学問」は特にこの昔ながらの大学に保存されています。これは実は、明治期以前の日本と似ていますよね。管野
それは本当に私もそう思う。
庄本
例えばヨーロッパの初期の大学では、先生が自分で生徒を集めるんですよ。だから自分の授業に人気がないと生徒が来ないんです。
管野
つまり、先生が選んでいるんじゃなくて学生が選んでいるというわけで、例えば自分で法律を学びたい学生がギルドというかそういうのを作って、そしてお金を出し合って有名な先生に来てもらう。オックスフォードやケンブリッジ、フランスのソルボンヌもそうやってできていってる。
庄本
そうですね。
管野
だから世界中から学生が集まってきて、そうすると学生や先生が集まってきたら当然色んなお店も出てくるわけで、大学を中心にして街ができる。それがオックスフォードとかケンブリッジだから。国が作って下に下ろすのではないわけです。先生と生徒の結びつきが学問の出発点なんです。
日本の近代教育

庄本
日本であれば、ちょうど欧米の大学の原型に似ているのが「私塾」でしょう。例えば福沢諭吉が学んだ緒方洪庵の適塾であるとか、吉田松陰の松下村塾であるとか。この私塾のラインは最終的に私立大学として明治以降続くことになるんですけど、日本の場合そこに国立大学がどーんと入ってきますね。国立大学の基は江戸時代にあった藩の学校である「藩校」。この二つの流れが西欧のように並列せず、「藩校」側に大きく傾いたんです。
管野
私塾も本来は非常に熱い力がたぎっていたんですよ。例えば吉田松陰はペリーの船に乗ろうとしたり非常に行動的。自分自身が熱血ですよね。彼は学問も非常にある人ですが、行動も起こす。先生が熱く語り、行動し、その思想や行動が正しい・間違っているは関係なく、己の信じるところを熱を込めて学問とともに語ると。そういうものがいかに人に影響を与えるかを私塾は見せてくれます。わたしは、教育の一つの理想の形が私塾にあったような気がするんですよ。それが明治時代になったら私塾はあんまり発展しないで、まあ、国立大学のモノマネの私立に転化してしまう。そこが日本の教育にとっては悲劇でした。
庄本
明治の初年あたりだと結構政府も揺れているんです。一般人に幅広い知識を伝えて自由主義的な教育をしようとする人々もいっぱいいたんですけど、相次ぐ戦争と軍隊からの要請もあって変わってしまう。結局、日本の富国強兵っていうのは、やっぱり「強兵」なんですよね。帝国主義の時代ですからね、アヘン戦争なんかを見て幕末から知識人はずっと危機意識を持ち続けてきた。
管野
日本人は幕末の頃に情報がどんどん入ってきますから、お手本にし続けてきた中国が、ある意味一日で敗れるところを見せられると危機感も芽生えます。中国思想がどうとか言っても鉄の塊の砲弾が飛んできたら中国の帆船なんかひとたまりもない。力がすべてだ、と。で、近代国家っていうのはイコール軍事国家ですよね。だから、教育制度も改革したけれどもすぐに留学生をどんどん欧米に派遣していく。面白いのは教育制度を作るのと同時に言葉を統一しようとしたんですよ。『国語元年』というNHKのドラマでやっていたけれども、当時は津軽の人と薩摩の人と話しても通じないんですよ。それがある意味自由でもあるんですけどね、特色豊かな地方分権国家として。
庄本
地方分権国家っていうのは非常に豊かな個性を持っていますが、近代国家になるためにはそれを統一しなきゃいけない。国語を統一する理由もまた、戦争ですね。上官の命令がなまってるとわからない。
管野
近代軍隊っていうのは命令が下ったらすぐ動かなきゃならないので、言語が統一されてないと戦えないんですよ。戦争以前の問題(笑)。尋常高等小学校の教科書は「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ(咲いた 咲いた 桜が咲いた)」。片仮名じゃないですか。これが標準語だった。つまり北海道から沖縄まで全部テキストを統一して言語を統一する。で、話が飛びますけど1980年代に愛知と千葉は管理教育が酷いと言われた。西の愛知に東の千葉。ちょうど私が塾講師になった頃です。すごいのは清掃するときには「掛け声清掃」。一斉に「イチ、ニ、イチ、ニ」とかやらせる。そして何かというと集めて歌を歌わせるんです。修学旅行でも江戸川台駅でまずみんなを整列させて歌を歌わせる。N中学校なんかは休み時間に国歌を言わせるんですよ。その瞬間に全員直立不動。それからH中とか野田の中学校もみんな班活動、連帯責任。班の中で一人でも中間テストで50点以下取ると全員が連帯責任で立たされるとか。こういう班活動は軍隊帰りの教師が持ち込んだとか色んな説があるんですけど、つまり日本の場合の初等中等教育と軍事教育、軍というのは非常に親和性が高いものになってしまっている。それが70代から80年代まで残っていたんです。だから日本の悲劇とは、ある意味富国強兵の軍人を作る教育の下請けとしての教育をずっとやってきたことかもしれません。僕が小学校からやってきた「前へならえ」っていうのは要するにまっすぐ直線になれってことですよ。つまり、列が乱れていたら困るということですよね。こういう画一教育が良しとされていた。しかも戦争が終わったにもかかわらず、ある種中央集権国家が残っていて、それが戦後の高度経済成長と非常にマッチしたわけですよ。規格大量生産とかね。
庄本
しかもアメリカから、今までは敵対していて入って来なかったクオリティーコントロールの技術とかがどーんと入って来ましたからね。
管野
そう、QC(品質管理=クオリティコントロール)活動と言ってね。戦後の日本の企業がQC、QCって言ってキャンペーンを張りました。ただ日本の場合偉かったのは下からも持ち上げていくというか、上からのQCじゃなくて下から、少しでも欠陥品をなくすにはどうするべきか工員同士が話し合うとか。それこそ日本の労働者のクオリティーが高いんですけど。日本人の労働者の質は画一教育のおかげで諸外国よりは凸凹がないんですね、皮肉なことに。だから労働者の質が恐ろしく高いということが日本の高度経済成長を支えた。
庄本
そうすると戦前までの画一教育、自由のない教育はよかったということになる。それが戦後の高度成長にマッチしたわけですね。「覚えろ覚えろ、先生の言ったとおりに書け、いい学校に行けるぞ」。いい学校に行って何になるかというと、大企業のサラリーマンだったりエリート公務員だったり。でも1970年代に高度経済成長がある意味終わりを遂げて、80年代に一気に矛盾が出てきますね。
管野
それが1970年代後半から中学校を襲った校内暴力。当時不良生徒を中心にみんな机・椅子ぶん投げたり教師を殴ったり。彼らが言ったのは「先生さぁー、なんで俺たち勉強しなくちゃなんねえんだよー、言ってくれよー」。とても重要な問いだったと思いますね。「自分のためだよ」「自分のためってなあに?」「良い高校良い大学入って、そしたら良い会社に行けるぞ。」それは経済的に保証されて一生困らなくなる。つまり食うに困らない社会、たったそれだけの目標だったということです。
庄本
当然納得いかない生徒も出てきますね。もっと人間っていうのは多様じゃないの? ミュージシャンをやってても俳優をやっててもいいじゃないか。そういう選択肢も実際はあるわけですが、学校教育の場においては国家目標を優先して「そんなものは不安定だからダメだ」と。そういう形ですよね。
管野
他にも、60年代の大学紛争で学生運動をやってた連中。彼らってエリートなんですよ。エリート意識が非常に高い。で、自分たちは良い大学に行ったけど、大学に行く人もまだまだ全員じゃなかった。自分たちは恵まれていたから大学にも来られたし、大きな企業に行ったりする。そうして気がつけば日本の資本主義を促進させて、労働者から搾取するという国家目標の一部になっていく。それでいいのかっていう疑問ですね。エリート意識の裏返しであって鼻持ちならなかったけれども、ある意味本質を点いていたと思いますね。このシステムはおかしい、狭すぎるっていう(笑)。
庄本
窮屈だってことですよね。
管野
そう、窮屈だと。大企業に行くっていうのは、それってただの歯車じゃないかと。その直感は正しかったなと思いますね。
庄本
官僚になったり企業のトップになっていく、いわゆるエリート層というのは、既存の受験勉強を勝ち抜いてきた優勝者じゃないですか。だけど実は日本の場合、一人に権力が集中しないですし、影に隠れちゃう部分がある。だから、優勝者のはずなのに、テレビとか観ても謝罪会見を開いているだけの人みたいに見えちゃうところがあると思うんですよね。ある本で読んだんですけど、日本人ほど、そういうトップエリート層というのを尊敬しない国民はいないっていう…
管野
うん、珍しいですよね。
日本人の特性
庄本
管野先生が80年代までのことをおっしゃっていましたが、私は90年代に主に学生だったんですけど、むしろ80年代の人たちって幸せだったかな、とすら思うんです。私なんかの世代だと、もう「何のために勉強するのか」なんて問いを発することすらしない状況でした。問いを発しても意味が無いというか、どうせ答えてくれないだろうと。校内暴力もほとんどないですし。で、学校側も、カタチだけというのはちょっと変ですけど、自由にしよう、と言い出した。だからぶつかる対象もないし目指す対象もない。
管野
うん、90年代はなんかそれ、わかるなぁ。それまではずっと画一教育をやってきて、70年代80年代からぶち壊す動きが出てきて、80年代は学校側も管理色を強めたわけですよ、危機感持って。でも方向が違うってわかって今は形だけの自由は与える。だから今は形だけの自由が蔓延している。それでいて誰も責任をとらない。画一教育とか管理教育が悪いみたいに私は言ってますけど、必ずしも悪いことばかりではない。その分、教育者や学校が責任もかぶる。でも今はそれもないですね。家庭で責任を持てと。うちの子も小学生なんですね。先日学校から紙が来て、プールの授業のときの健康は家庭でチェックしてくれと書かれていました。健康に問題ありません、と誓約させられるんですよ。つまり何かあったら学校の責任じゃないですよ、と。風邪を引いたら寝かせておけばいいかというと「病院で診断書もらってきて」って言われる。とことん責任をとらないぞという変な官僚主義というか、形だけの自由は与えるけれども責任はとりませんよ、みたいな状況になっている。むしろ悪くなったのかな(笑)。
 庄本:アハハ…。形だけの自由という話でいえば、私も中学校で「自由というのは責任が伴うんだ」って怒られたことがあるんです。疑問に思って、自由と責任にどういう関係があるのか深い話を聞きたいと思っても何も教えてくれない。「君たちは自由だよ」と言っておきながら、何かすると叱られる。責任が伴う、というならば、その責任って何だ、と。今ちょうどマイケル・サンデル教授の『これからの正義の話をしよう』という本が流行ってますけど、結局一番根本の部分を教えてもらえなかったことから来る「根本」への欲求なのかもしれません。
庄本:アハハ…。形だけの自由という話でいえば、私も中学校で「自由というのは責任が伴うんだ」って怒られたことがあるんです。疑問に思って、自由と責任にどういう関係があるのか深い話を聞きたいと思っても何も教えてくれない。「君たちは自由だよ」と言っておきながら、何かすると叱られる。責任が伴う、というならば、その責任って何だ、と。今ちょうどマイケル・サンデル教授の『これからの正義の話をしよう』という本が流行ってますけど、結局一番根本の部分を教えてもらえなかったことから来る「根本」への欲求なのかもしれません。管野
自由と責任の話はさっきの「トップエリートの尊敬」の話につながりますね。欧米に遅れているというと語弊があるけれども、日本の場合、なにか問題が起こると常に連帯責任で社長はお飾り。あとはみんなでごちゃごちゃ話し合いをして、その代わり責任の所在はわからない。これは確かに欧米の文化からすれば「よくない状況」ですが、日本の変な伝統でもあるわけです。伝統的な日本文化の良い面は、例えばあまり格差をつけない、自然に話し合いをしながら誰も傷つかないようにうまく解決策を作り出す、あるいは誰もが痛みを分けあって誰もが少しだけ傷つく、あるいは誰もが犠牲にしない、そういう知恵みたいなものを発動するところにあります。外国のように指揮官が全部握って全部俺の言うとおりにやれではなくて、下からも「ちょっとそれ、おかしいんじゃないですか?」と言えるような、ある意味本当の民主主義かなあとも思えるんです。
庄本
最近だとヨーロッパのほうが逆にそういうコミュニティを目指しているところがあって、結構あべこべになっていますよね。
管野
そう、一方で日本人の悪いところといえば責任の所在が曖昧。ひと言で言ってしまえば最終責任は誰というのがいつも消えてしまうのが問題ですよね。これはよいところと表裏一体をなしている。
庄本
だからこそ、日本的な感性の部分は保持しつつ、やはり最終的に責任が取れる、そういう人間というのがやはりこの後の社会には必要になってくると思うんです。この連載を通して、21世紀の教育に対して塾に何ができるんだろうかということを結構考えてきたんですけど、今後必要とされる人材は、大量生産では作れないなと痛感しています。日本人の伝統を保持しつつ欧米的な自由と責任の観念も理解出来る人間って、一言で言えば非常に「スケールの大きい」人間ですよね。最初に管野先生がおっしゃっていた、システムありきではなくて、人と人との間で直結して血の通った関係が必要だと思うんです。システム重視で作られた教育がうまくいかなくなってしまったのは分かったわけですから。
これからの教育
管野
まあそう言っちゃうと、すぐ政治的な発想をする人は「国じゃなくて民間だよね」と言うけれども、私はそういうことを言いたいんじゃなくて、今おっしゃる通り、師と弟子が血の通った結びつきをする、教えたい人と学びたい人が結びつくのが教育の原点なんです。ソクラテスだって弟子が集まってきて対話してますよね。いかに人間は生きるべきかというのがみんなが関心あることで、それを理解するには色んな知識がいるわけですよ。「物質は何からできている」とか「宇宙の成り立ちは何だ」とかそういう議論を通じて、じゃあ我々人間はいかにして生きるんだ、あるいは人間関係はどうあるべきか、と会話を通して学んでいく。人間は本来そういう動物なんですよ。ストーリーが必要。小学生だからこれ教えちゃダメ、中学生だからまだ難しいからわからない、じゃなくて、ある種大学で教えるような哲学であったり経済であったり、それを生きたものとして語るんだから小学生でもついてこられる。
庄本
小学生こそ「えーっ、それは何?」「ハイ、ハイ!」ってみんな言います。「こんなこと言ったら先生に笑われるかな」とか「答えが違うかな」じゃなくて、疑問があれば疑問に対して対話をして一緒に連れて行く。それが教育の本来の姿だとすると、小学生のほうがまだ疑問を言うからやりやすい(笑)。中一で一次関数をやり中二で二次関数をやることになっているから、中一では二次関数は難しいですよとかそういう問題じゃありません。例えば関数なら関数というものについて生徒と議論したら生徒も興味を持つ。興味関心を持ったら何関数を教えようが三角関数教えようが生徒はついてこられる。
 管野:それはまさに私が「塾」を作る時に思ったことです。塾を作る時に思ったのが全くそれです。だからツールはなんでもいい。教科書じゃなくてもいいじゃないですか。実際漫画も使いましたよ。『少年時代』という藤子不二雄Aの作品ですが。主人公が戦中、疎開先ですごくいじめられる。いじめる村の少年というのがすごく悪魔的なんですよ。悪い奴なのかいい奴なのか最後までわからない。あれは非常に深い。下手な文学作品を読むより『少年時代』という漫画を読んだほうが人間の深淵を見られると思ったから、それを私は教材に使ったわけです。で、生徒も漫画だったら読みますよね。別に生徒に媚びているとかじゃなくて、あの時点で私はあの漫画が一番人間の複雑さを教えるには適していると思ったから使ったんです。あるいはビートたけしの毒舌エッセーがあって、「この間銀座の姉ちゃんと飲んだよ」とかいう文から入るけど、実は政治経済のことを語っているわけですよね。非常にシンプルな言葉で日本のシステムの矛盾を語っている。それを読んだほうが話を進めやすいと。そこを「教科書じゃないとダメ」ということではないわけですよね。
管野:それはまさに私が「塾」を作る時に思ったことです。塾を作る時に思ったのが全くそれです。だからツールはなんでもいい。教科書じゃなくてもいいじゃないですか。実際漫画も使いましたよ。『少年時代』という藤子不二雄Aの作品ですが。主人公が戦中、疎開先ですごくいじめられる。いじめる村の少年というのがすごく悪魔的なんですよ。悪い奴なのかいい奴なのか最後までわからない。あれは非常に深い。下手な文学作品を読むより『少年時代』という漫画を読んだほうが人間の深淵を見られると思ったから、それを私は教材に使ったわけです。で、生徒も漫画だったら読みますよね。別に生徒に媚びているとかじゃなくて、あの時点で私はあの漫画が一番人間の複雑さを教えるには適していると思ったから使ったんです。あるいはビートたけしの毒舌エッセーがあって、「この間銀座の姉ちゃんと飲んだよ」とかいう文から入るけど、実は政治経済のことを語っているわけですよね。非常にシンプルな言葉で日本のシステムの矛盾を語っている。それを読んだほうが話を進めやすいと。そこを「教科書じゃないとダメ」ということではないわけですよね。庄本
そういう発想を考えた時に、これからの教育というのはもう一度教育の原点に戻ってシステムとしての国家主導の教育じゃなくて、一人ひとりを伸ばすということを考える必要がありますね。
管野
そうです。やっぱり師と弟子が対話をしていくという非常に贅沢な教育です。でも、これ、お金もかかりますよ。ヨーロッパの貴族や中産階級なんかは昔から家庭教師です。で、日本はまだ家庭教師まではいかないけど私塾があるんですよ。本当は学習塾はこの私塾の伝統を引き継いで行かなきゃいけないんだけど、今はどこもプレップスクールですよね。
庄本
要するに大学や高校、中学という公共の教育システムを助ける「予備校」ですね。
管野
予備校的な教育の形は、今のシステムを維持する側にまわっているという意味ではもう古い。だから普通に、シンプルに、「なぜ勉強しなければいけないか」を考えるところから始めて、勉強を通じて人間性を高めていく。それをやる教育が今必要なんです。食うための時代じゃないでしょ。いくら不況だといったって明日食べるご飯がない人は多くはいませんよね。その段階を過ぎているのに、教育システムだけは「食べるものがなくなったらどうしよう」に合わせた、マズローの心理学で言うとあのずっと下の…
庄本
生理的欲求…
管野
生理的欲求の段階。その段階に合わせたシステムなんですね。多くの人は、良い学校→良い就職先、良い家庭が幸せと考えてるけど、それはサバイバル(安全)欲求でしかない。人間のもっとも原始的なレベルの食えなくなる恐怖にもとづく発想だよね。今はもっと高いレベルでの欲求を満たす時代。だからこれからの勉強は本当の意味で自分を高める欲求にもとづくものでなければ。
管野
今の子どもたちが40代50代になる時にはおそらく社会の価値観もものすごく変わっているはずです。これからは、一人ひとりの人間の人生はその人の能力に応じたものになる。どこかの学校へ行った、どこかの会社に入ったからって均一な人生ではなくて、その人が小さければ小さな幸せで終わるだろうし、その人が大きなものがあれば大きな幸せがあると言いますね。その土台を作ろうと。大きく育つ土台を作りたいと我々は考えています。師と弟子の関係を中心にしてですね。先生は一生懸命教えてくれて語ってくれたと。そういう先生との交流を思い出すことによって、自分もまたある種のリーダーシップを取れるんですよね。人々に真実を伝えていくような情熱を持った人間、それをやっぱり育てることができたらなと。そういうふうに思いますね。
庄本
本日はどうもありがとうございました。
管野
ありがとうございました。